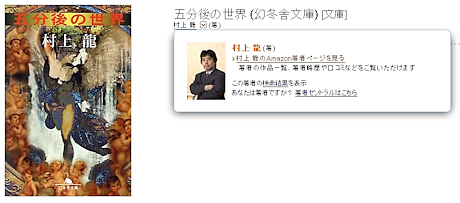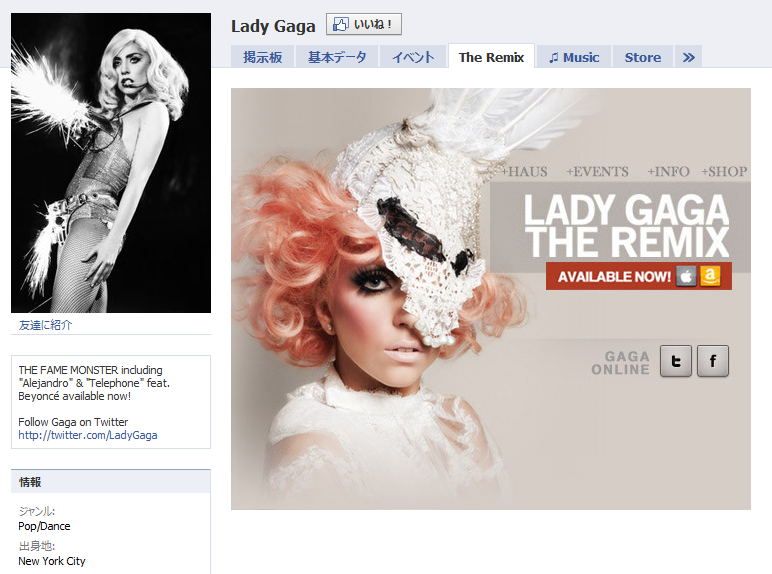追記:そもそもの前提が正しくないという意見もあるようですが、自分でTVCMを見ていないので判断がつきかねます。サラ金パチスロ云々の話は着想のネタと捉えて頂ければ幸いです。メインストリーム化に伴い、自制心が低く割引率の高い層の取り組みが重要となり、ソーシャルゲームはそこに適応しているというのがポイントです。
テレビ広告を実施する企業はどんな企業かについての議論が面白かった。
Togetter – 「佐々木俊尚@sasakitoshinao氏の、ソーシャルゲーム評、ソーシャルゲームネタと、それに対するツイートまとめ」
RT @igi: サラ金(消費者金融)→パチスロ→法律事務所→ソーシャルゲームとTVCMに出稿する広告クライアントの主流は21世紀以降移り変わってきたけども、業態は違えど”これらのビジネスターゲット”が全く変わっていないことに注目すべき
テレビを使って広告を打つ企業はサラ金、パチスロ、法律事務所(債権回収など?)、ソーシャルゲームと移り変わってきたが、そのターゲットは変わっていないという指摘だ。
これはテレビという媒体がターゲットとしている層はほぼ決まっていることを考えれば自然だ。十年ぐらいでテレビの主な視聴者が変わることはない。
RT @shinjifukuhara: 20年近くテレビの前線にいますが、いくつかの視聴者クラスターが消えていることに気付きます。。でもボリュームゾーンはほぼ変わってないと思います。RT @rionaoki: 先程からテレビ広告のターゲットに関するツイートがRTされていますよね。
これについてはテレビ局で働く人の発言からも裏付けられている。消えたクラスターは今は主にインターネットでニュースなどをチェックし、娯楽番組ではなくYouTubeやニコニコ動画を楽しむような層だろう。
テレビでの広告は非常に高くつくので、サラ金・パチスロ・法律事務所・ソーシャルゲームといった業界はテレビでしかリーチできない集団を相手にしていると考えていいだろう。但しテレビの主な視聴者がその集団であるとい考えるのは早計だ。例えこういった広告がターゲットとしている人が視聴者の少数派であっても、他の手段でリーチできず、かつ大きく利益に貢献すればよい。
では、過去にテレビ広告に出稿していたサラ金・パチスロ・法律事務所に共通する顧客はどのような人々だろうか。ギャンブルに興じ、借金を重ねてしまうという人間像が浮かび上がる。自制心が弱く、割引率の高いグループだ。ソーシャルゲームはこういった消費者相手の商売と考えると実によく出来ていることが分かる:
- 基本ただ:最初は課金せず、どんどん特典を用意する。今後、ゲーム内アイテムを後払いで購入可能にしたり、一ヶ月以内にキャンセルしなかった場合だけ費用が発生するといった課金方法が登場するだろう(もうしてるかもしれないが)。
- 育成系:どれだけ自分がハマるかを予想できない。ソーシャルゲームのほとんどはだんだん面白くなっていく育成系だ。これは旧来のネットゲームとも共通する。
- 招待制度:ソーシャルゲームは、友達を招待させることで拡散する。自制心が弱い人は、自分が友達を招待すると、それが原因で辞めることもできなくなる(ピアプレッシャー)。これもネットゲームと同じだ。マルチ商法じみた招待制度も登場するかもしれない。
- 仮想通貨:Facebookなどでは既にプラットフォーム独自の仮想通貨がつくられている。これはゲーム内で通貨を稼ぎ、他のサービス・物品の購入に当てることができることを意味する。パチンコの景品交換所に近い仕組みを創りだすことが可能だろう。
プラットフォームはソーシャルゲームをさらに流行らせるため、共通仮想通貨制度の普及、課金システムの改善を行う必要がある。例えば、仮想通貨制度に加わりクレジットカードなどの決済手段とリンクさせると一定の金額をプレゼントしたり、残高がマイナスの場合にはプラットフォーム自体のアカウントを停止するといったことが考えられる。