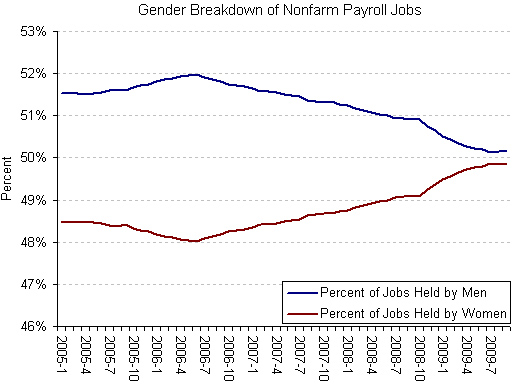ニュースのローカル化が叫ばれているなか、ハイパーローカル(hyper local)なサービスを提供するサイトがある:
EveryBlock — A news feed for your block
We aim to collect all of the news and civic goings-on that have happened recently in your city, and make it simple for you to keep track of news in particular areas. We’re a geographic filter — a “news feed” for your neighborhood, or, yes, even your block.
Everyblockの目的は小さな地域(blockないしneighborhood)に関連する情報をフィルターすることだ。公的機関の提供する情報、ニュースの記事、ブログのエントリー、Yelp、Craigslist、Flickrに至るまで位置情報とタグされている・できる情報の総量は爆発的に増えている。情報化社会におけるキーはフィルタリングだ。膨大な情報があれば個々の情報の価値はなくなる。それらをまとめても価値はたかが知れている。有り余る情報から意味のあるものを選び出すことで価値が生じる。
最初は検索エンジン式の情報収集から始められるだろう。ネット上から位置情報を持つ情報をマッピングする。重要なのはその次だ。できる限りユーザーを集め、彼らが新しい情報やコメントを書き込む環境を作る。そのエコシステムを確立できるかがこのビジネスの鍵だろう。
面白い試みだが今後の競争は熾烈だ。位置情報を持つ情報を集めることは他の企業にも可能だ。特にGoogleが同じことを始める可能性は非常に高い。また、ユーザーから情報のインプットがあってもそれ自体を他のサイトが収集してしまうこともある。この中で競争に勝ち抜き、どのような収益モデルを作ることができるのだろうか。