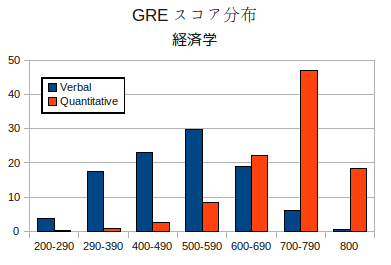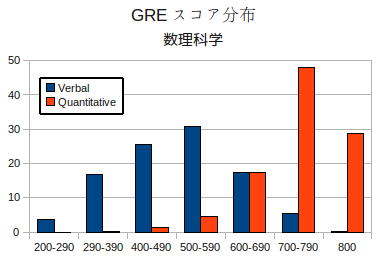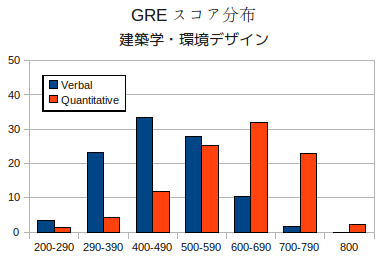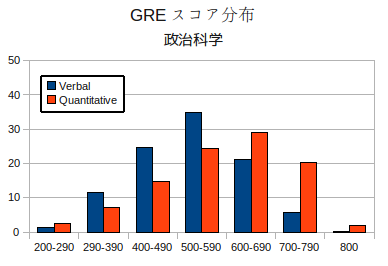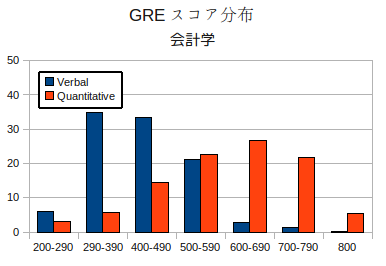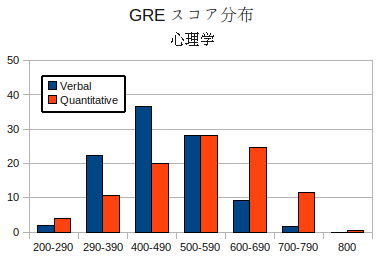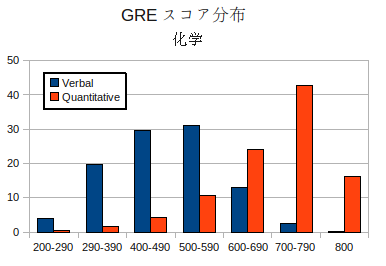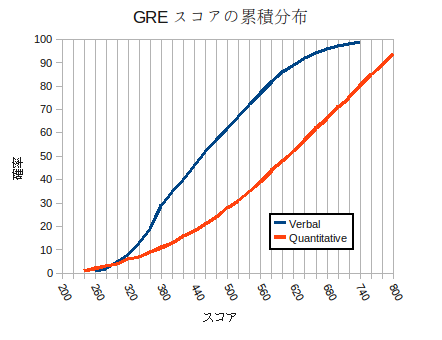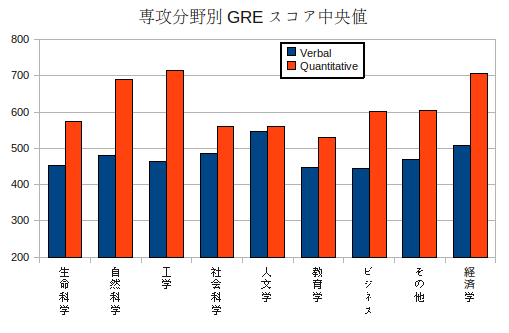101を謳いながら内容が101でない本ブログですが時には教科書的な内容ということで、価格戦争が何故起きるのか、どうやったら防げるのかについてのバランスのとれた解説がThe New Yorkerから(ジャーナリストが書いているため読みやすく、経済学と英語を勉強したいかたに最適):
The Amazon Wal-Mart price war : The New Yorker
価格競争というのは値下げ合戦のことだ。複数の会社が同じような商品の値段を下げて相手に勝とうとする。ここでは最近話題になったWal-MartとAmazonの間での競争が取り上げられている。
Wal-Mart began by marking down the prices of ten best-sellers—including the new Stephen King and the upcoming Sarah Palin—to ten bucks. When Amazon, predictably, matched that price, Wal-Mart went to nine dollars, and, when Amazon matched again, Wal-Mart went to $8.99, at which point Amazon rested. (Target, too, jumped in, leading Wal-Mart to drop to $8.98.)
オンライン書籍最大手(かつeCommerse最大手だろう)Amazonに対し、売上世界一のスーパーマーケットチェーンであるWalmartが値下げ合戦を始めたという話だ。Wal-Martは10冊の新刊を含むベストセラーをわずか$10で売り出し、Amazonはそれに追従、最終的にWal-Mart、Amazon、Targetの三者が$9付近の価格を提示した。
これ単独でみれば消費者には望ましい。しかし、売っている側はどうだろう。
Since wholesale book prices are traditionally around fifty per cent off the cover price, and these books are now marked down sixty per cent or more, Amazon and Wal-Mart are surely losing money every time they sell one of the discounted titles. The more they sell, the less they make. That doesn’t sound like good business.
書籍の卸売価格は表示価格の約半分だそうで、値引き率が60%を越えるこれらの本は売れば売るほど赤字だ。その中でさらに価格を下げて競争相手から客を奪うことはさらに損失を広げることになる。これが経営者から価格戦争が嫌われる理由である。
From a game-theory perspective, price wars are usually negative-sum games: everyone loses. A recent study found that, if competitors do match price cuts, industry profits can get cut almost in half.
参加者全員の利益は価格戦争によって大きく減る。そのため企業は価格戦争を避ける方法を模索する。それは主に二種類ある:
前者はそもそも価格競争が成立しないようにすることである。製品が非常に似ているため価格での競争が起きる。コンピュータでいえばAppleのように独自の製品を打ち出すことが他の企業との競争を減らすことにつながる
後者は他の企業と協力して価格競争を避けることである。但し、複数の企業が共謀して価格を釣り上げることは独占禁止法に違反する。そのため、企業は直接にコミュニケーションを取ることなく価格競争をする意志がないことを競争相手に伝えようとする。その時のキー・ポイントは
- 価格を下げた場合どれだけの利益を得られるか(気付かれるのにどれだけかかるか)
- 報復行為の程度
- 実際に報復に出ることの合理性(credibility)
となる。一つ目は製品差別化と重なる。差別化が十分であれば相手が価格を下げてもそれほど顧客を奪われなくなる。二つ目は合意を破った場合の対処だ。報復が大きければ抑止効果がある。最後は報復が可能だとして実際にそれを実行に移せるかだ。事後的に報復を実行することが合理的でなければ、空脅しに過ぎない。以下は典型的な手段である:
- 一方的な宣言
- 業界団体設立
- 余剰な生産設備の確保
- プライス・マッチング
1は価格安定が必要であることを経営者などが発言することだ。価格に関する合意が違法なのであって、一方的な発言は違法でないためだ。2は業界団体を通じて価格情報をやりとりする。相手の価格を簡単にモニターできれば協力関係にある企業が合意に違反しているかどうかをすばやくチェックでき、違反するインセンティブを減らせる。3は合意に違反した場合の報復を可能にする方法だ。もし相手が価格を下げてきた場合には急速に生産を拡大して簡単に価格競争を起こせる(生産容量が足りなければ相手のシェアを奪えない)。また価格競争が低コストで起こせることは、もし合意を破ったら報復するという信頼性(crediblity)を上げる。最後は消費者に対して競合他社の価格が自社よりも低かったら値下げすると約束することだ。これは相手が価格を下げた場合に消費者が教えてくれるという情報面でのメリットがある上、自動的に価格戦争に突入するという状況を作ることでコミットメントの問題を解決する。
次の一節は若干誤解を招くので注釈しておく:
Sometimes it’s rational: when a company is genuinely more efficient than its competitors, lowering prices is usually a smart move.
価格戦争に突入することが合理的なことがあると述べているが、これは分かりにくい語法だ。経済学的にいえば、価格競争に突入した企業にとってその行動が個別に合理的であることは当然だ。そういう行動を取った以上それは合理的な意思決定の結果としてしか捉えられないためだ。
ここでのrationalは価格を下げることが明らかに価格競争を避けることよりも望ましいことがあるという意味だろう。これは自社が競合相手よりも遥に効率的である場合に該当する(自社の独占価格が相手の限界費用よりも低い)。
では今回のWal-MartとAmazonとの競争についてはどうか。
It’s to lure them online, away from big booksellers and other retailers, and then sell them other stuff. Usually, price wars wreak havoc because they erode the pricing power of an entire business. But, because this price war involves just ten items, its impact on revenue will be small, and outweighed by the positive effects of all the publicity.
これは価格競争というよりも広告のセール品のようなものだと捉えられる。目的は本を買いたい人を自社サイトに連れてくることだ。一旦アカウントを作って、支払い、購入を済ませれば次からオンラインで本(ないし他の製品)を買うのは簡単になる。またスーパーのセール同様品目は限られているため損失も小さい。
The real competition in this price war is not between Wal-Mart and Amazon but between those behemoths and everyone else—and the damage everyone else is incurring is deliberate, not collateral. Wal-Mart and Amazon have figured out how to fight a price war and win: make sure someone else takes the blows.
では何故Amazonは全く同じ本で価格を下げたのか。Wal-Martと戦うためというのは考えにくい。Amazonの顧客はオンラインで本をよく購入する比較的情報技術に明るい人だ。Wal-Martで少し本が売っているからといって客が移るとは考えにくい。多くのオンライン書店を価格比較しているユーザーは一部流れるかもしれないがそれはAmazonにとって特に望ましい顧客層ではない。
むしろAmazonはこの「価格戦争」に乗ることで、Wal-Martと協力したという指摘されている。AmazonはWal-Martと競争することで、オンラインで本を買っていない層へ自らをアピールすると共に、ネット上では価格競争があり本が安く買えるという事実を彼らに知らせることができた。これはAmazonにとってもWal-Martにとってもプラスだ。
同じようなことはオンラインvs既存小売店以外の文脈でもありうる。例えば、iPhoneアプリが互いに価格競争を行うことでiPhoneのユーザーを増やせれば長期的にはプラスになりうる。しかしこの例が示すように一筋縄にいかない。iPhoneの魅力が上がってもAppleがiPhone自体の価格を上げてしまえばAppleの利益が増すだけでアプリ開発者には利益がない。またAppleが何もしなくとも他のアプリ開発者の参入もあり得るし、競争相手が競争を辞めない可能性もある。