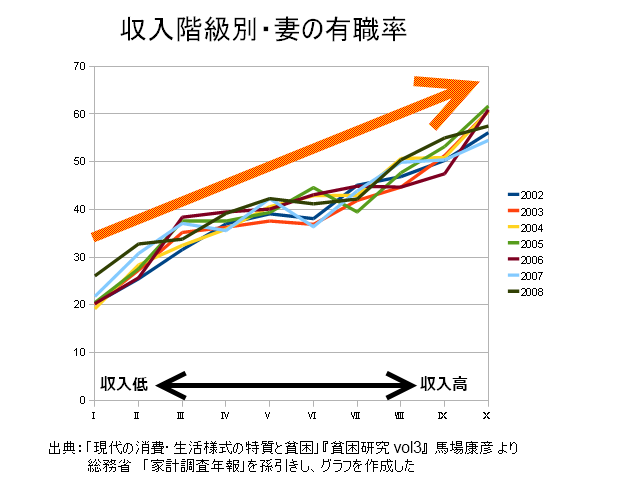デジタル化した市場で雑誌の未来は新聞のそれよりも明るいという話:
雑誌の未来、新聞よりは明るい? 光沢は失えど先行きに希望 JBpress(日本ビジネスプレス)
データベースのメディアファインダー・ドット・コムの試算では、北米では今年1~9月期に383誌が廃刊になった。だが、ここ数カ月、生き残った雑誌は意 外な自信を見せ始めている。紙媒体についてもデジタル版についても、雑誌の命運は必ずしも一緒にスタンドに並ぶ新聞と同じではないと考えるようになったの だ。
新聞より雑誌がうまくデジタル化に対応できるのはその通りだろう。しかし、元記事で挙げられているその理由はあまり正確なように思えない:
- 時間に敏感でないのでアグリゲーターの影響を受けない
- E-bookリーダーが雑誌なみに画質を再現
私は雑誌の未来が明るい理由は次のようなものだと考える:
- デジタル化は市場を広げるためニッチなセグメントで雑誌が活動するのを容易にする
- 新聞はもともと様々な情報を集めるアグリゲーターなのでGoogle Newsのようなアグリゲーターと競争になるが、雑誌は直接競争にはならない
- 雑誌の内容はニュースではなく著作物であり知的財産として保護される
1はネットがない時代を考えるとわかりやすい。紙媒体がカバーできる面積には限界がある。大都市でニッチな産業が発展するように、ネットは情報面での人々の距離を縮めニッチなビジネスを可能にする。
2は見落とされがちな点だ。新聞各社はGoogle Newsを批判する。それは単に彼らがGoogle Newsと同じ土俵で戦っており負けているからだ。もともと新聞というビジネスの本質は、情報の生産者というよりもアグリゲーターだ。新聞社が記者やコラムニストを囲っていたのは単なる垂直統合に過ぎない。垂直統合を有利にしていた技術・経済的背景が変化し、記者やコラムニストがデジタル時代に新聞社から分離していくのはその帰結だ。もともとアグリゲーターとしての機能が小さい雑誌はGoogle Newsのようなサービスとの競争を心配する必要がない。
3は何度か述べているが、ニュースという事実を保護するのは技術的に難しい。雑誌の内容は普通の著作物なので単純にコピーされる心配はないだろう。
追記:はてなブックマークで
Google Newsには新聞は勝てないが雑誌は著作権というアドバンテージで勝てるという話。いまひとつ腑に落ちない。
とあるが著作権の話がメインではない。最大のポイントはGoogle Newsと新聞は競争相手だが、雑誌は勝てる・勝てない以前に同じ土俵にはいないってこと。もちろんそれゆえに雑誌は成功するっていうわけでもない。ニッチを狙うビジネスとメインストリームを狙うビジネスとでは最適な戦略が全然違う。