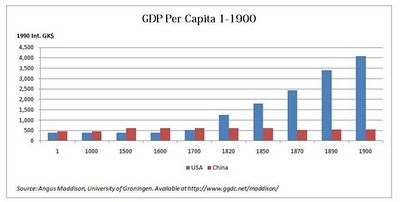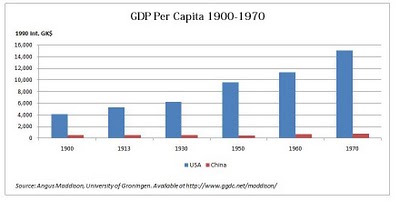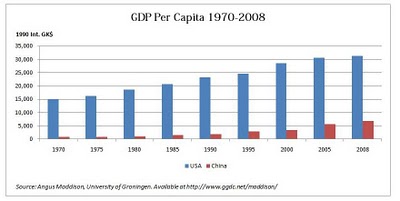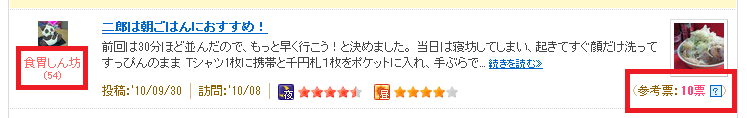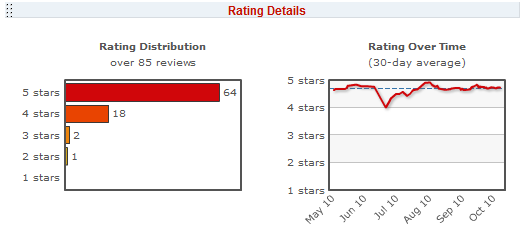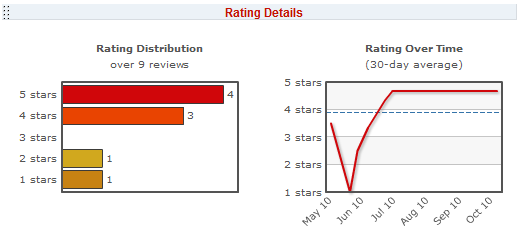出版社と印刷は違うので、電子書籍は出版社にとっての脅威ではない:
Will technology kill book publishing? Not even close
電子書籍が書籍の大きな部分を占めるようになるのは確実だ。読みたい情報をパッケージして届けるという機能を考えればそれが便利になることは消費者の利益になる(もっとも、その時に「書籍」というカテゴリー自体に何の意味があるかという話はあるが)。
しかし、このことは出版業界というものの行末が、グレーかもしれないが、真っ暗であることは意味しない。その理由が挙げられている。
Myth No. 1.Publishers are merely printers. That would be news to companies like ours, which don’t even operate their own printing presses. Publishers today are in the content business.
出版社は印刷所ではない。紙の書籍が激減すれば印刷所は困るが、出版社はコンテンツビジネスだ。私自身、最近紙の書籍を出版したが、出版社は印刷ビジネスではないのは明らかだった。実際、印刷自体は外注だろう。
Myth No. 2.Authors don’t need publishers in the digital age. Anyone who has ever written a book knows this to be false.
また、著者が出版社を必要としないというのも間違えだ。ある題材(この場合Facebook)について書くことができるかと、その題材が投入する資源に見合うだけの市場をもっているかを知っているかは違うことだ。
企業法務マンサバイバルさんも「この本を企画した編集者の慧眼はすごいと思いました」と指摘されているように、市場の需要と生産要素とを結びつけるのが出版のコアビジネスだ。生産要素の一つで非常にコモディタイズされている紙での印刷自体は言われているほど重要ではないはずだ。
These relationships are even more critical to a book’s success in the digital age. With the ascent of e-books, authors will need publishers to serve as digital artists who can bring words to life by pairing text with multimedia features such as audio, video and search.
書籍におけるデザインの仕事もなくならない。ある程度の分量の文章を効率的にみせるためにはデザインが必要で、これは素人にはなかなかできない。インターネットの普及は紙媒体での仕事を減らしたかもしれないが、WordpressのようなCMSのテンプレート作成への需要が創出された。
むしろ出版「社」にとって危険なのは、会社として軽量化を目指す過程でこうしたコア機能を外注してしまうことだろう。編集者やデザイナーといったネットワークが外にでてしまえば出版社にはディストリビューションしか残らない。
P.S. この記事をTweetされていた大原ケイさんの本は読んでおきたい。
大原 ケイ
アスキー・メディアワークス
売り上げランキング: 14084