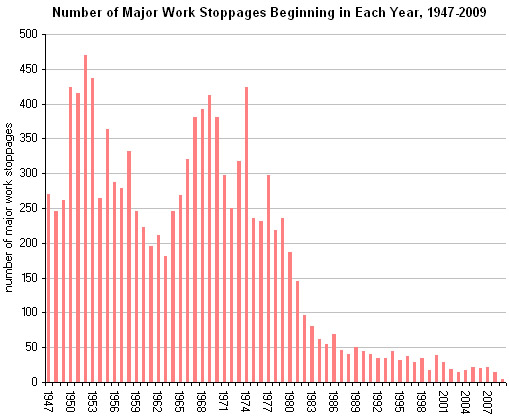就活に反対する行進を取り上げた英文の記事: Japanese Students Abandon Studies for Job-Hunting Gantlet – International – The Chronicle of Higher Education
By graduation this spring, many students will have spent 18 months and hundreds of hours preparing for and attending job interviews and recruitment fairs, all but abandoning study for months on end.
卒業前の18ヶ月間、数百時間かけて面接準備なんかをする日本の就活が紹介されている。長い期間にわたって就職の準備をするのはこちらでも変わらないが、その形態はインターンをこなし経験をつけるというもので、面接の準備に比べると生産的に思える。
“I had a student who got two—one from a local bank and another from a hotel,” he says. “She really wanted the hotel so accepted that. But the bank said, ‘You can’t do that’ and interrogated her for six hours, saying ‘You’re disloyal’ and so on. Finally the student’s father came and called the police.”
銀行とホテルから内定をもらった学生がホテルへの就職を決めたところ、銀行に不誠実だと尋問され警察沙汰になったという例が挙げられている。おそらく普通のアメリカ人はこれを読んでも何を言っているのか分からないだろう。親が出てくるのも不可解だろうが、それ以前にこんなことが起きたら確実に訴訟沙汰だ。
Japan is not unique in effectively forcing college students to look for jobs before graduation, but Mr. Slater says the system does demand that they start early. “They must begin figuring out what they want to do by second year,” he says, “and it becomes really heavy-duty in third.”
就職のために学生が在学中から活動するのは珍しいことではないが、日本ではそれが非常に長期に渡るという。将来何をしたいか二年目には考え始めなければならないのは大変と指摘されている。二年目に仕事のことはなど全く頭になかった自分はその時点でレールから外れていたと思うと感慨深い。 就活の問題については各所で取り上げられていることと思うので、採用どころか就活自体したことのない私が意見することはない。しかし、長期の就活を解消するには大学の学生評価の機能を上げるしかないだろう。成績が評価に訳に立たないのであれば、企業が欲しい学生を先に(面接のような方法で)確保しようとするインセンティブはなくならない。 ただ、就活という制度が持つメリットも見過ごしてはいけないだろう。日本の就職活動が苛烈なのは事実だが、企業が新卒を採用する制度が確立しているのは、自分で見つけなくてもいいという点で学生にとってはメリットでもあ る。新卒至上主義は就活へのプレッシャーではあるが、第一には新卒の学生に有利なものだ。大学が大衆化した現在、卒業生がここまで就職先を確定させている 国も少ないだろう。アメリカでインターンが一般化していることの背景には、経験のない学生が仕事をもらえないので、経験を積むことができないというサイクルがある。
“It’s ridiculous. We don’t have time to mature as people or as students,” says Shingo Hori, a philosophy major at Waseda. “We’re forced to spend all our time looking for work.”
それにしても、 この一節は日本の外の人が読んだら笑ってしまうかもしれない。Philosophy Majorが就職が大変なんて言っても自業自得としか思われないし、大学卒業前に自分がmatureする時間がないなんて堂々と言えたことではないだろう(二十歳前後の期間が重要な点は同意するが)。