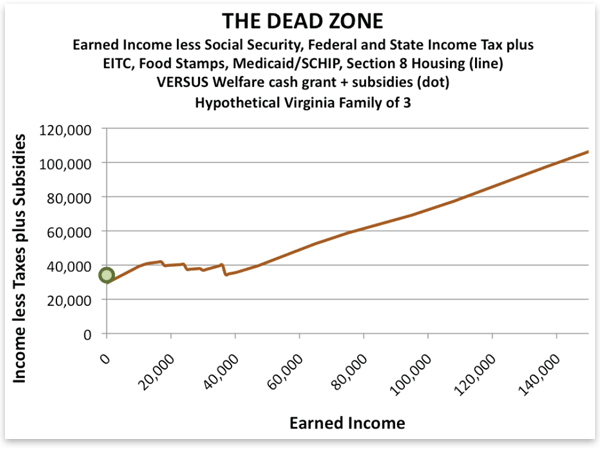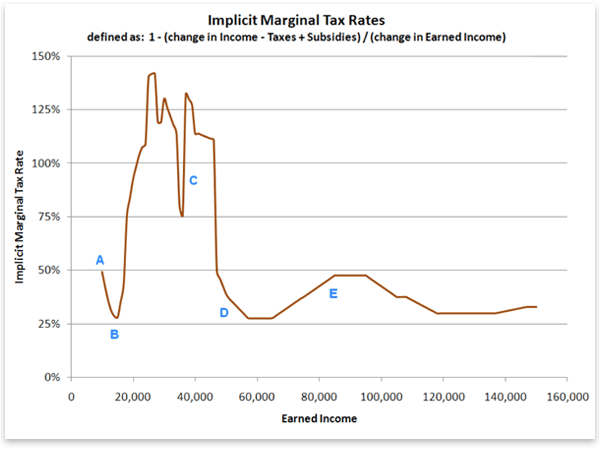日本メーカーのカスタマーサービスについての記事:
アゴラ : これでいいのか?最近のカスタマーサービス- 上村敏
元の文章は読みにくく、論点が整理されていないが、コメント欄で補足されている:
該当の件は液晶テレビの購入時の問題で、BS/CSチューナーを搭載している考え商品を購入したのですが、実際には搭載されない商品でした。ネットであわ せてパラボラアンテナも同時購入していたので、店頭での購入であればまずこのような事態にはなっていなかったのでしょう。販売店およびメーカーサイドでは開梱後の返品および交換は一切受けられないとに回答でした。消費者センターの見解ではBS/CSチューナー非搭載などのデ メリット表示が不十分であるとの指摘をうけましたので、販売店及びメーカーに文書にて回答をお願いいたしました。その結果販売店より商品交換の回答が、電 話にて(文書ではなく)あり昨日商品交換が完了しこの問題自体は解決いたしました。
小売店が商品説明のような正の外部性(=他の小売店も得をする)の強いサービスを行う場合、再販売価格維持制度がなければそのサービスが過小供給され社会厚生が低下することが知られている。
再販売価格が拘束されていなければ、小売店が頑張って商品説明を行っても他の安い店で買われてしまうからだ。ここで商品説明は一種の公共財となっている。
公正取引委員会による再販売価格拘束の取り締まりに加えて、ネット販売の普及により消費者が安い他の店で購入することはより簡単になった。この環境下で十分な商品説明が行われないのは自然な帰結だろう。
しかし、だからといって再販売価格拘束が正当化されるわけではない。再販売価格を固定することは小売店間の競争を妨げるという問題があるからだ。その例外に当たるのが再販制度の認められている著作物だ。
ちなみに、
ただ私のように消費者センターまで問題を持ちこまなければこの程度の問題が解決できないのかという疑問がありました。
とあるが小売店同士の競争を確保するためにはある程度仕方ないだろう。商品情報が過小供給される以上、消費者はよりよく情報を集めて商品を購入する必要がある。小売店は商品販売にかかるリスクを負っており、表示不十分で間違って購入された商品の返品を受け入れるインセンティブがない(消費者センターに叩かれれば受け入れるようだが)。
アメリカでは家電製品はレシートがあれば無条件で返金に応じるという商習慣があるということを思い出しました。ただ結婚式に必要なビデオカメラを買い、終了後そのカメラを販売店に返品にくるといった例もあり、まったく信じられない商習慣であると感じました。
アメリカ式の返品制度には反対のようだが、解決策の一つであるのは確かだ。また、ある程度の問題はコストダウンのために受け入れるしかないという意見について、
熾烈な国際競争では決して生き残れません。
と述べているがそんなことはないだろう。現にアメリカのカスタマーサポート(ないしカスタマーサービス一般)は日本とは比べ物にならないほど低い。またそもそも小売店レベルのサポートの話が国際競争と何の関係があるのかもわからない。