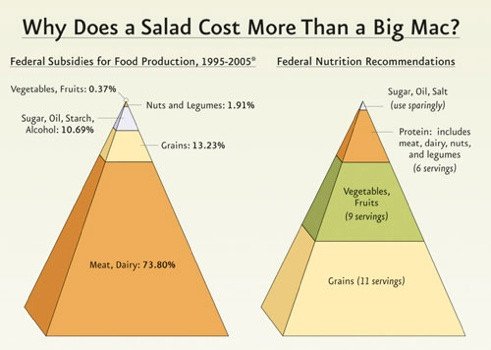電子書籍に関する懇親会が開かれたそうだ:
政府は17日、本や雑誌をデジタル化した電子書籍の普及に向けた環境整備に着手した。[…]国が関与して国内ルールを整えることで、中小の 出版業者の保護を図る狙いがある。
しかし規格統一の狙いが中小の出版業者というのはどういうことだろう。
電子書籍の形式は各メーカーが定めており、共通のルール、規格がない。端末ごとに読める書籍が限定されるほか、「資本力で勝るメーカーに規格決定の主導権を握られると、出版関連業界は中抜きにされる恐れがある」(総務省幹部)との指摘がある。
日本だけでしか流通しない独自規格を官民で整備したとして、それが誰にメリットになるのだろう。Amazon, Apple, Googleなど先進的な企業が競争した結果生き残る規格に日本発の規格が競争できる訳はないので、国外展開は絶望的だ。当然、電子書籍の流通やリーダーなどに関しても取り残されるだろう。消費者にとっても海外で使われている優れた規格が日本では利用できないという結果になりはしないだろうか。
また、テクノロジーが進歩したときに流通の一部が「中抜き」されるのは当然のことだ。出版の場合だけ政府が心配するのは何故だろう。
ちなみに懇親会のメンバーは総務省で公開されている。現職以外のプロフィールぐらい載せて欲しいと思うが、生まれ年だけ簡単に調べてみた(Googleで検索してすぐに見える情報で正確性は保障できないので間違いがあればご指摘下さい)。
- 安達俊雄 シャープ株式会社代表取締役副社長:1948年
- 足立 直樹 凸版印刷株式会社代表取締役社長:1935年
- 阿刀田 高 作家・社団法人日本ペンクラブ会長:1935年
- 内山 斉 社団法人日本新聞協会会長・株式会社読売新聞グループ本社代表取締役社長:1935年
- 相賀昌宏 社団法人日本雑誌協会副理事長・株式会社小学館代表取締役社長:1951年
- 大橋信夫 日本書店商業組合連合会代表理事・株式会社東京堂書店代表取締役:1943年
- 小城武彦 丸善株式会社代表取締役社長:1961年
- 金原優 社団法人日本書籍出版協会副理事長・株式会社医学書院代表取締役社長:調査中
- 北島義俊 大日本印刷株式会社代表取締役社長:1933年
- 喜多埜裕明 ヤフー株式会社取締役最高執行責任者:1962年
- 佐藤隆信 社団法人日本書籍出版協会デジタル化対応特別委員会委員長・株式会社新潮社取締役社長:1942年
- 里中満智子 マンガ家・デジタルマンガ協会副会長:1948年
- 渋谷達紀 早稲田大学法学部教授:不明・一度大学から退職されています
- 末松安晴 東京工業大学名誉教授・国立情報学研究所顧問:1932年
- 杉本重雄 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授:不明・1977年に大学卒業
- 鈴木正俊 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長:1951年
- 高井昌史 株式会社紀伊國屋書店代表取締役社長:1947年
- 高橋誠 KDDI株式会社取締役執行役員常務 コンシューマ商品統括本部長:1961年
- 徳田英幸 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長兼環境情報学部教授:1952年
- 長尾真 国立国会図書館長:1936年
- 楡周平 作家・社団法人日本推理作家協会常任理事:1957年
- 野口不二夫 米国法人ソニーエレクトロ二クス上級副社長:不明・1982年ソニー入社
- 野間省伸 株式会社講談社副社長:1937年
- 三田誠広 作家・社団法人日本文藝家協会副理事長:1948年
- 村上憲郎 グーグル株式会社名誉会長:1947年
- 山口政廣 社団法人日本印刷産業連合会会長・共同印刷株式会社取締役会:1937年
生まれ年から類推するに70歳以上が7人、60-70歳が7人、50-60歳が4人、40-50歳が3人となっている(3人は不明だが50代、60代、70代一人ずつといったところか)。
年齢が高いことが一概に悪いとは言わないが、電子書籍という新しいメディアを論じるに当たってもう少し若い世代の意見を取り入れることはできないのだろうか。50歳以下だと産業再生機構から丸紅社長に就任した小城武彦氏、ヤフーの喜多埜裕明氏、KDDIの高橋誠氏となっている。
ネットの利用に関しては喜多埜氏と高橋氏の二人についてTwitterのアカウントが確認できた(@kitano123、@makjob)。あとは三田誠広がかなり古風な個人サイトを運営されている。しかしこれらも例外であり、参加者のテクノロジーの利用は進んでいないと見るべきだろう。。
業種別では、大学4、作家4、出版4、書店3、印刷3、ネット2、メーカー2、通信2、図書館1となっている(これに省庁関係者が加わる)。既存の出版の仕組みから利益を得ていると考えられる作家・出版・書店・印刷が14に対して、電子書籍を推進するであろうネット・メーカー・通信は6しかいない(作家は本来ニュートラルと考えられるが参加者はどなたも既に業界団体の上に立つ立場であるからして、既存の仕組みを支持していると考えるのが妥当だろう)。言うまでもなく経済学関係の人は見当たらない。
「中小の 出版業者の保護を図る狙い」とある割には中小出版業者の代表は少なく、むしろ大手出版社関係者が多い。金原氏が社長をつとめる医学書院が中小出版業と言えるが(訂正:年齢が違っている模様です)、医学書院の出版物の価格を考えると保護を図るという主張は消費者にとって受け入れがたいのではないだろうか。
最後に、シャープの安達俊雄氏および丸紅の小城武彦氏は旧通商産業省出身だ。経済産業省が関わる懇親会なのだからこういった情報は公開するのが筋だろう。
追記:金原氏の情報が違っているという情報を頂いたので注記しました。