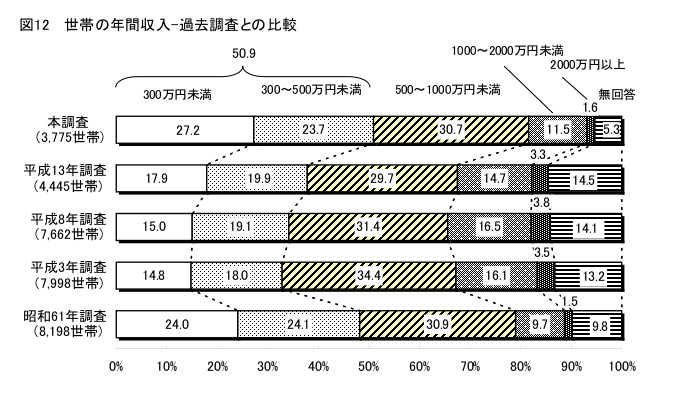最近、アメリカのアカデミックな労働市場についての「ポスドクとは アカデミアに仕事が少ない!編」を読んだ。当事者の目から説明されている良い記事だが、テニュア制度の存在意義についてはちょっと単純化しすぎなので補足したい:
まずテニュア(Tenure)というのは教授の終身雇用のことだ。ポスドクや助教授(Assistant Professor)は任期付きのポストで、研究実績がたまってきたらテニュアの審査を受ける。うまくいけば終身雇用が約束され、だめなら他の大学に移る。この制度は日本での導入も進んでいる。
元はといえばテニュア制は、学問的にメインストリームでなく、リスキーで過激な主張をする学者さんを、政治的な糾弾、弾劾から守り、学問の自由を保証するために存在した制度です。現在では、かなり形骸化し、雇用の安定を保証する以上あまり存在価値のない制度とも言えます。
ではこの制度はなぜ存在するのか。一つは学問の自由の保証だ。しかし、エコノミストの認識はそうでもない:
The economists who have analyzed tenure have seen it as a solution to the problems created by the special nature of academic employment instead of a protection for academic freedom.
テニュア制度は学問の自由というよりも特別な労働関係に対応するための仕組みだという。いくつかの問題が挙げられているが最も重要なのは以下だろう:
Carmichael (1988) argues that tenure exists within academic environments because worker-professors are called upon to select new members.
テニュア制度は既存の教授が新任の教授を選ぶという仕組みのためにあるという。どういうことか。
When the university has full information about the abilities and alternatives of incumbents and candidates, tenure is not part of the optimal solution. The least productive and most expensive professors will be fired and replaced by new candidates. However, when the university does not have full knowledge and incumbents have better information, the university will have problems getting incumbents to identify the best candidates if it plans to follow an optimal hiring and firing strategy. An incumbent cannot rule out the possibility that he or she will be fired in the future to make room for a candidate. Thus, if the university expects its incumbents to tell it who the good candidates are, the incumbent’s signals about candidates must not affect he incumbent’s probability of being retained.
根底にあるのは、研究者を採用することの難しさだ。例えば数学者を雇うとしてどの候補者を採用するか決めるのは数学者に任せるのが最適だろう。実際、大学教授は大学教授によって選任される。しかし、もし既存の教授の雇用が守られていなければ、彼らに公平な選出を期待するのは難しい。優秀な若手を採用すれば自分の雇用が脅かされるからだ。
同じことは高度に専門化された他の分野でも当てはまるだろう。例えば弁護士事務所であれば出世するとパートナーになる。弁護士事務所がパートナーシップを利用する理由は法律以外にもいろいろあるだろうが、ベテランに実質的な終身雇用を与えるという機能もあるだろう。
もちろん終身雇用を約束することは、働くインセンティブを失わせるが、そこはトレードオフだろう。インセンティブの低下には、学部全体を解散することでも対応できる。学部全体のパフォーマンスが低い場合に解雇されうることは、優秀な若手を避けることにはつながらない(むしろ採用するだろう)が、仕事をするインセンティブになる。