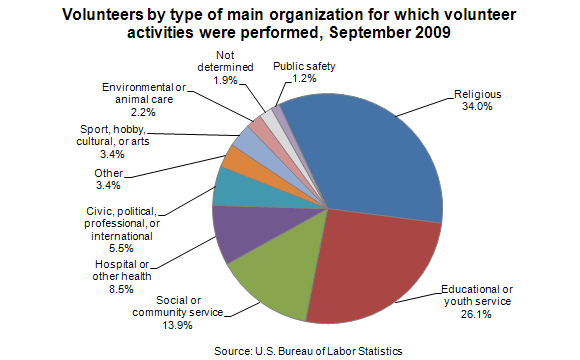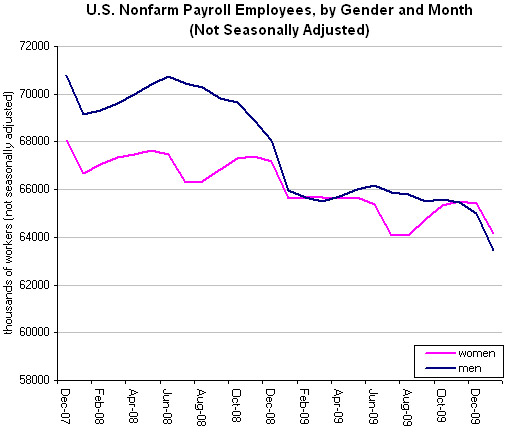どうも最近首を傾げるような記事が増えていて残念なアゴラから:
アゴラ : 自分が悪い 助けてといわない若者 – 原淳二郎(ジャーナリスト)
自分が悪いと考えてしまう若者が増えているという問題(?)が取り上げられている。20代後半の私も「若者」に含まれるだろう(しかしいつから「三十代の若者」などという概念が登場したのだろう)。
現在の不遇な環境、不幸は社会の責任ではないし、まして親の責任でもない。だからいくら困窮しても助けてといえないのだそうだ。30代の若者の現象らしい のだが、日ごろ学生を見ていて同じように感じることがある。
実際、問題に直面する原因の最も大きなものは自分の行動だろう。また、他人のせいにしたところで問題が解決するわけではないので、そういう考え方を持たない方が本人にとってもいいはずだ。
心優しいのか、誰が悪い、社会が悪い、教師が悪いなどといわない。毎日の生活に被害者意識が薄 い。
そしてそれは「心が優しい」からではない。単に、頑張ればもっといい状況にできたという事実認識と、被害者意識を持つより自分のせいだと考えた方が生産的だと知っているだけだろう。このような認識の何が問題なのかよくわからない。
毎日の生活に被害者意識が薄い。私の子どものころは、毎日食うものに困り、親からは家業にこき使われ、何もいいことがなかった。なぜこんなに自分は不幸な のか、と思うと同時に、自分が悪いから不幸なわけではない、周りが悪いのだと考えた。事実社会はまだ貧しかった。家業は二度も倒産した。社会への関心政治 への関心はそのころから生まれた。
確かに、貧しい社会でそういう育ちかたをすれば、社会や親が悪いと考えるのは分かる。しかし、現代の社会はそこまで貧しくないし、そういう環境で育つ人は昔に比べて相当減ったはずだ。
だからテレビがいうところの自分が悪いという若者の論理がよく分からなかった。大不況になってもストライキひとつ起きない。デモもない。ネットでぶつぶつ不平をつぶやくらいだ。
現代社会において、多くの人の成功は自分の努力にかかっている。他の要因もあるが、自分が一番重要な要素だと多くの人が認識しているだけだろう。そしてその認識は基本的に正しい。
もうデモやストだけが社会的表現手段だった時代ではない。ネットなどでいくらでも表現できる。
まさにその通りで、不況でもストライキやデモのような非生産的な行動はしない。そんなことをしなくても「ネットでぶつぶつ不平をつぶやく」だけで、不平を世間に知らせることができるのだから当たり前だろう。不平が社会に流れていくチャンネルが変わったのだ。
日本には彼らが貧しいのは自己責任だという風潮がある。いつからこんな風潮が広まったのかは知らないが、不当に弱者に追いやられた人々が不満の声をあげられない社会をわれわれはいつの間にか作り上げてしまった。
これは風潮というよりも、時代が変わっただけのことだ。個人の努力ではどうにでもならない貧困がはびこる社会では貧しいことは主に社会の問題だが、努力すれば成功できる社会においては貧しいことが一義的には個人の問題となる。日本は大方前者から後者へと移行した。そしてそれは喜ぶべきことだろう。ご自身で指摘されているように、「不満の声」はネットを利用して簡単にあげられる。
もちろん、このことはより個人が努力によって成功できるように仕組みを改善していくことを妨げるものでは全くない。しかし何でもかんでも親のせい、社会のせいと言っている社会には未来がない。勉強ができないのは親や環境のせいだと文句をいっていた子供が成功しているだろうか。
追記:困っている人がそのことを社会に伝えるのは重要だが、本人が自分の問題だと認識していなければ援助しても効果がないとも言えるか。
P.S.
母親から毎月1500万円も贈られながら「知らなかった」人には、貧しくて声もあげられない人たちの心情などとても想像できないことだろう。
結局この一文を言いたかっただけのような気もする。しかしそういう政治家を選んだのは有権者であることも事実だ。