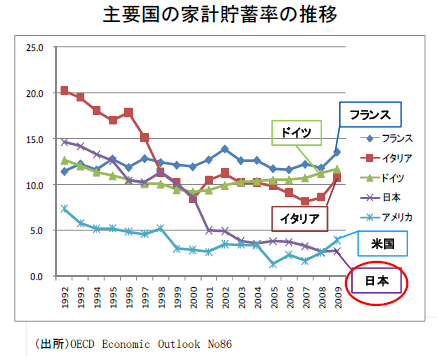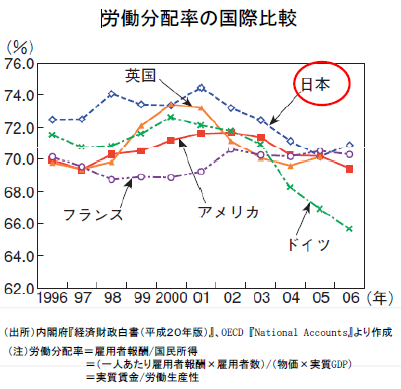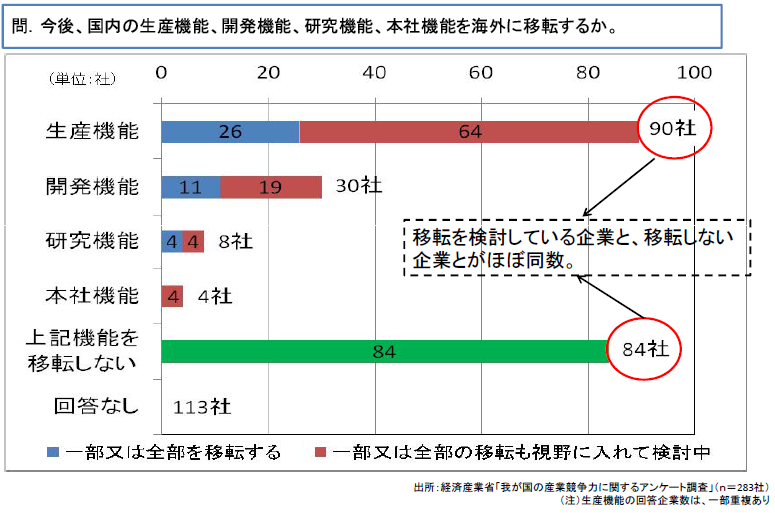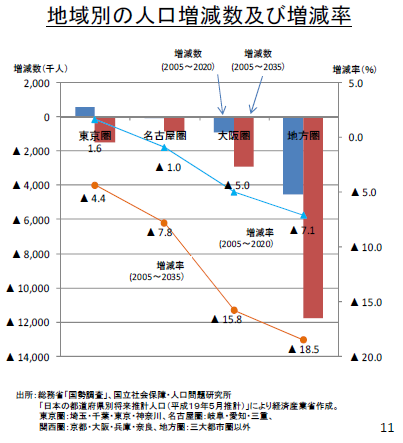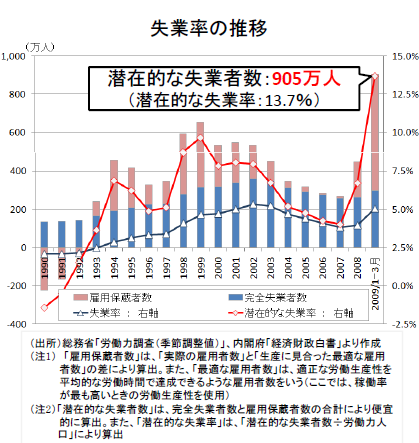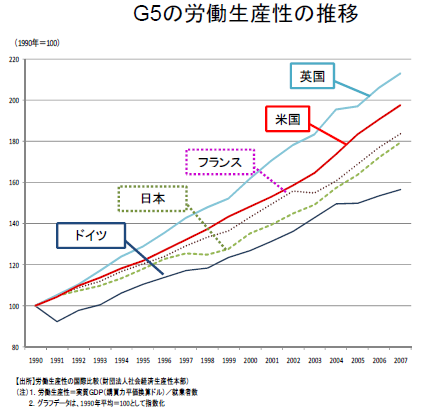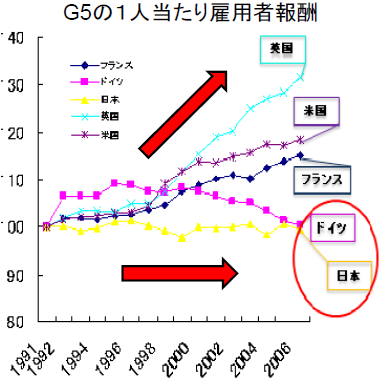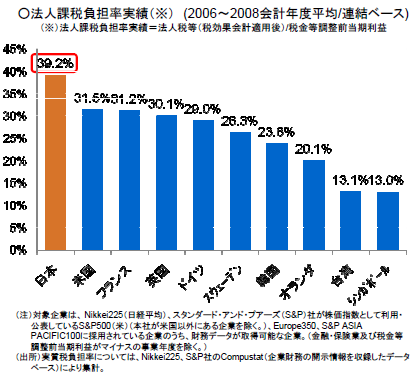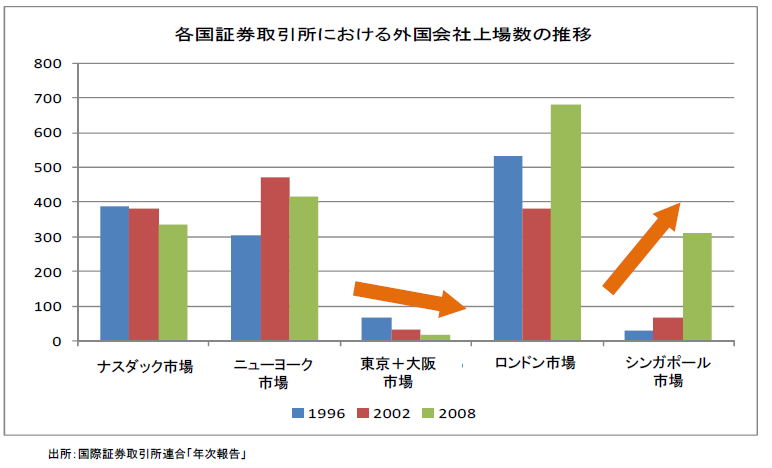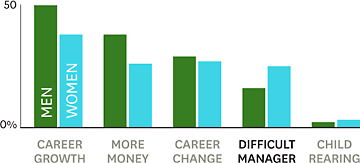メディアが陥っている問題について非常によくできた記事の紹介。
News is a lousy business for Google too
There is a widespread myth that search engines have taken profits away from news websites.
サーチエンジンがニュースを提供する企業から利益を横取りしているという主張はよく聞く。しかし、ネット上でニュースが儲からないことはサーチエンジンがなくても十分説明できる。
The internet upended this model by 1) providing a new delivery method for classified ads (mainly Craigslist), 2) increasing the supply of newspapers from 1-2 per location to thousands per location, thereby driving the willingness-to-pay for news dramatically down, and 3) unbundling news categories, making cross subsidization increasingly hard.
三つの理由が挙げられている。一つはCraigslistを代表とするクラシファイド広告の登場だ。こういった広告は旧来の(アメリカの)新聞にとって大きな収益源であった。二つ目に地域独占が解消し、ひとつの地域でたくさんの新聞を購読できるようになった。三つ目はニュースを分けて販売できるようになったためニュース以外で稼いでニュースでお金を使うということできなくったことだ。
これらはどれも紙媒体に存在した紙媒体のボトルネックがなくなったことにより生じている。配布コストが下がれば地域独占はなくなり競争はまし、バンドルを維持できなくなる。クラシファイド広告もまた旧来はバンドルされていたコンテンツの一つだ。
ここまではこのブログでも何度も述べてきたことだが、次の話が面白い。
Even Google doesn’t make money on it.
ニュースはGoogleにとってすら儲からないという。実際にAfgranistan warで検索しても広告が表示されない。あまりにも収益が少ないからだ。
Big money-making categories include travel, consumer electronics and malpractice lawyers. News queries are loss leaders.
Googleが利益をあげるのは旅行や電化製品、それに訴訟ネタだという。実際、去年の最も高いキーワードはMesotheliomaだった。ニュースで利益を出せないのは検索エンジンに横取りされているからではなく、そもそもニュースが生み出す利益が非常に小さくなったためだということがよく分かる。